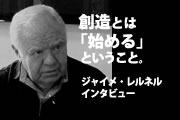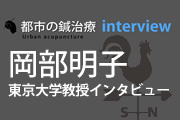新着データ
新着データ
(東京都)
人口の減少に伴って、現代の都市ではまるでスポンジのように空き家や空きビルが広がっています。それらの空間をわたしたちはどう活かせるのでしょうか。『都市をたたむ』などの著作で知られる東京都立大学の饗庭 伸(あいば・しん)教授。都市問題へのユニークな提言が注目されています。饗庭教授は2022年、『都市の問診』(鹿島出版会)と題する書籍を上梓されました。「都市の問診」とは、いったい何を意味するのでしょうか。「都市の鍼治療」提唱者の服部圭郎 龍谷大学教授が、東京都立大学の饗庭研究室を訪ねました。
お話:饗庭 伸 東京都立大学都市環境学部教授
聞き手:服部圭郎 龍谷大学政策学部教授
(神奈川県)
ビジネス、観光の両面で多くの人々をひきつける港町・横浜。どのようにして今日のような魅力ある街づくりが実現したのでしょうか。今回の都市の鍼治療インタビューでは、横浜市のまちづくりに詳しい、横浜市立大学国際教養学部の鈴木伸治教授にお話を聞きました。
(イングランド)
アヴィーバ・スタジオスはマンチェスターのアーウェル川沿いにあったグラナダ・スタジオ跡地に2023年に開設された、音楽、芸術を包含した文化施設である。マンチェスターはミュージシャンを輩出するという観点では、イギリスでも傑出した音楽都市であると考えられるが、それでも多くのミュージシャンは活動機会を求めて、また生活の基盤を求めてロンドンに出て行ってしまった。そのトレンドを逆転するためのシステムづくりをしていくうえで、このアヴィーバ・スタジオはまさに「ツボ押し」のような効果を発揮しつつある。
(鹿児島県)
縄文杉で知られる世界自然遺産の島、屋久島。その観光資源は優れているが、人口は減少傾向にある。島に8つある小学校のひとつ一湊小学校の児童数も少なくなっていた。そのようななかで家族単位での留学を受け入れる「黒潮留学」の制度が導入された。高齢者のボランティアで始めた学童保育も功を奏し、「コミュニティで子どもを育ててくれる」安心感が生まれている。
(東京都)
東京にある下北沢という街は特別のオーラのようなものを纏っている。このオーラをつくりだしているのは強烈な個性を有する店主が営んでいる個店群である。そして、そのようなお店の象徴ともいえるのが1975年に開業したジャズ・バー「レディ・ジェーン」であろう。
(フィンランド共和国)
ヘルシンキのカンピ地区にある1936年に建てられた商業ビル、ラシパァツィ。取り壊しの計画が持ち上がるたびにヘルシンキ市民が反対をしてきた。そして2018年8月、このビルはアモス・レックス美術館として生まれ変わる。また従来バス・ターミナルとして使われていた隣接するスペースはユニークな意匠の公共広場へと変貌した。
(イタリア共和国)
ウルビーノはイタリアのマルケ州北西部にある人口14,000人ほどの町。城壁に囲まれた歴史的市街地区には観光客の車は進入することができない。このため城壁の外に二つの広大な駐車場を設けた。そのうちの一つ、メルカトール広場の地下駐車場からは、車を停めた後、人々は垂直導線で城壁内にアクセスすることができる。
(フランス共和国)
アヌシーはフランス東部にあるアヌシー湖岸に位置する都市。旧市街を通り抜けるティウー運河は絵葉書となるような美しい景観をつくりだし、「アルプスのヴェニス」と呼ばれている。今でこそ美しい運河であるが、ちょっと前までは湖に建ち並ぶホテルやサマーハウスからの生活排水により、その水質は汚染されていた。現在のこの運河の美しさは、悪化した運河、そして水源であるアヌシー湖の水質を浄化したことで獲得されたものなのだ。
(イングランド)
リバプールのマージー川沿いにあるロイヤル・アルバート・ドックは建物・倉庫群からなる港湾施設である。操業停止後の1970年代には荒廃した時期もあったが、その歴史的な重要性を保全し、次世代に繋げることを強く意識したリノベーションが行われた結果、現在はリバプールの主要観光資源として年間400万人以上の人が訪れている。
(フィンランド共和国)
フィンランド中部の都市タンペレ。その産業発展に寄与してきた繊維会社が工場を閉鎖すると、都市の中心部に近接して広大な工場跡地が出現した。この再開発では、既存の産業遺産ともいえる建物を再利用することで、現在の人々のニーズにしっかりと対応しつつ、新たな都心部の魅力を創出させることに成功した。
 インタビュー
インタビュー
(建築家・元クリチバ市長)
「よりよい都市を目指すには、スピードが重要です。なぜなら、創造は「始める」ということだからです。我々はプロジェクトが完了したり、すべての答えが準備されたりするまで待つ必要はないのです。時には、ただ始めた方がいい場合もあるのです。そして、そのアイデアに人々がどのように反応するかをみればいいのです。」(ジャイメ・レルネル)
(横浜市立大学国際教養学部教授)
ビジネス、観光の両面で多くの人々をひきつける港町・横浜。どのようにして今日のような魅力ある街づくりが実現したのでしょうか。今回の都市の鍼治療インタビューでは、横浜市のまちづくりに詳しい、横浜市立大学国際教養学部の鈴木伸治教授にお話を聞きました。
(福岡大学工学部社会デザイン工学科教授)
都市の鍼治療 特別インタビューとして、福岡大学工学部社会デザイン工学科教授の柴田 久へのインタビューをお送りします。
福岡市の警固公園リニューアル事業などでも知られる柴田先生は、コミュニティデザインの手法で公共空間をデザインされています。
今回のインタビューでは、市民に愛される公共空間をつくるにはどうすればいいのか。その秘訣を伺いました。
(地域計画家)
今回の「都市の鍼治療インタビュー」は、九州の都市を中心に都市デザインに携わっている地域計画家の高尾忠志さんへのインタビューをお送りします。優れた景観を守ための開発手法や、複雑な事業を一括して発注することによるメリットなど、まちづくりの秘訣を伺います。
(大阪大学名誉教授)
1970年代から長年にわたり日本の都市計画・都市デザインの研究をリードしてきた鳴海先生。ひとびとが生き生きと暮らせる都市をめざすにはどういう視点が大事なのか。
これまでの研究と実践活動の歩みを具体的に振り返りながら語っていただきました。
(クリチバ市元環境局長)
シリーズ「都市の鍼治療」。今回は「クリチバの奇跡」と呼ばれる都市計画の実行にたずさわったクリチバ市元環境局長の中村ひとしさんをゲストに迎え、お話をお聞きします。
(大阪大学サイバーメディアコモンズにて収録)
お金がなくても知恵を活かせば都市は元気になる。ヴァーチャルリアリティの専門家でもある福田先生に、国内・海外の「都市の鍼治療」事例をたくさんご紹介いただきました。聞き手は「都市の鍼治療」伝道師でもある、服部圭郎 明治学院大学経済学部教授です。
(龍谷大学政策学部にて収録)
「市街地に孔を開けることで、都市は元気になる。」(阿部大輔 龍谷大学准教授)
データベース「都市の鍼治療」。今回はスペシャル版として、京都・龍谷大学より、対談形式の録画番組をお届けします。お話をうかがうのは、都市デザインがご専門の阿部大輔 龍谷大学政策学部政策学科准教授です。スペイン・バルセロナの都市再生に詳しい阿部先生に、バルセロナ流の「都市の鍼治療」について解説していただきました。
(建築家・東京大学教授)
「本当に現実に向き合うと、(統計データとは)違ったものが見えてきます。この塩見という土地で、わたしたちが、大学、学生という立場を活かして何かをすることが、一種のツボ押しになり、新しい経済活動がそのまわりに生まれてくる。新たなものがまわりに出てくることが大切で、そういうことが鍼治療なのだと思います。」(岡部明子)
今回は、建築家で東京大学教授の岡部明子氏へのインタビューをお送りします。
(東京工業大学准教授)
今回の「都市の鍼治療インタビュー」は、東京工業大学准教授の土肥真人氏へのインタビューをお送りします。土肥先生は「エコロジカル・デモクラシー」をキーワードに、人間と都市を生態系の中に位置づけなおす研究に取り組み、市民と共に新しいまちづくりを実践されています。
(東京都立大学都市環境学部教授)
人口の減少に伴って、現代の都市ではまるでスポンジのように空き家や空きビルが広がっています。それらの空間をわたしたちはどう活かせるのでしょうか。『都市をたたむ』などの著作で知られる東京都立大学の饗庭 伸(あいば・しん)教授。都市問題へのユニークな提言が注目されています。饗庭教授は2022年、『都市の問診』(鹿島出版会)と題する書籍を上梓されました。「都市の問診」とは、いったい何を意味するのでしょうか。「都市の鍼治療」提唱者の服部圭郎 龍谷大学教授が、東京都立大学の饗庭研究室を訪ねました。
お話:饗庭 伸 東京都立大学都市環境学部教授
聞き手:服部圭郎 龍谷大学政策学部教授
 新着データ
新着データ インタビュー
インタビュー
 Back
Back