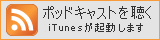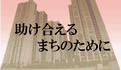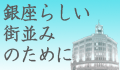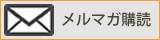2008年12月10日
輝く都市
■ライトアップの温熱効果
12月になると、夜の街がにぎやかになる。耳に響くクリスマスソングだけでなく、視覚的にもライトアップがやたら目に付く。明るく照らされた通りは、長く重苦しい夜の闇から心を解き放してくれるが、また寒い冬の街を暖かく感じさせてくれる効果もありそうである。そう思ったのは、数年前に中国東北地方(旧満州)のハルピンを訪れたときである。まだ10月だったが、夜の冷気は氷点下である。気温としては日中の方が高いに違いないが、視覚を含めた体感温度は夜の方が暖かいかもしれない。最初に見たときは、その大胆な配色に品の無さを感じたが、しばらくすると違和感が無くなり、前述の効果もあって、むしろ好ましく思えてくるから不思議である。

(写真左)ハルピン中心街の歴史的町並み、中央大街
(写真右)新華書店角の昼景と夜景
■現実のものとなった映画で見た近未来都市
前々号で紹介した階段と坂の街、重慶を嘉陵(ジャーリン)江の船上から見た臨江門付近の夜景は、西洋と東洋がミックスした怪しげな情景である。それはSF映画「ブレードランナー」の冒頭のシーンを思い起こさせる。もう四半世紀も前の映画ということになるが、そこで描かれていたのは環境が悪化した地球の近未来都市である。そんな悪夢を連想させる情景が、船上の私たちの眼前に展開したのである。一般に、ライトアップされた光景は細部が打ち消されて現実感が薄れ、ヴァーチャルな、幻想的な体験をもたらしてくれる。重慶で見た洋の東西の渾然としたこの光景はとても異様で、それが今日のちぐはぐな中国の現実を映し出しているようでもあった。

嘉陵(ジャーリン)江の船上から見た重慶・臨江門付近の夜景
■遊園地化する都市
エネルギー問題をはずして考えると、最初に述べた心理効果や防犯という面から、街は明るいに越したことはない。郊外にある最寄り駅から自宅まで、暗い道をたどるより、明るい空間の広がりを感じながら行く方が足取りも軽くなる。しかし、最近見かける光の演出には、にわか作りの遊園地のような子供っぽさが感じられる。ディズニーランドのライトアップの方がまだ増しである。街が楽しくなれば良いではないか、と言われればそれまでだが、日本の都市の夜景に、もう少し大人らしい品格が求められないだろうか。
今回のタイトルの「輝く都市」は、建築家、ル・コルビュジエが1930年代に提唱した理想都市を表す言葉でもある。高層ビルとオープンスペース、完備された道路網といった考え方は、20世紀後半の都市で実現されている。しかし今日では、その見かけの輝きに隠された、モダニズムの非人間的な面が批判されている。それと同じように、ライトアップの効果に隠されがちな輝く都市の本当の姿を見失わないようにしたいものである。

東京近郊の駅周辺で見られるライトアップとディズニーランドのライトアップ
(大野隆造)
- Permalink
- 東京生活ジャーナル
- 14:28
- in 05世界から見た東京